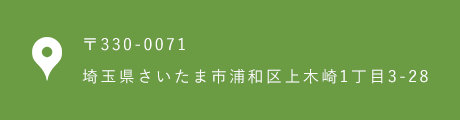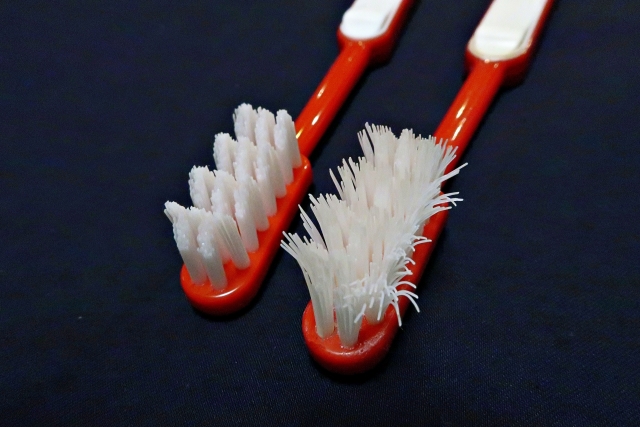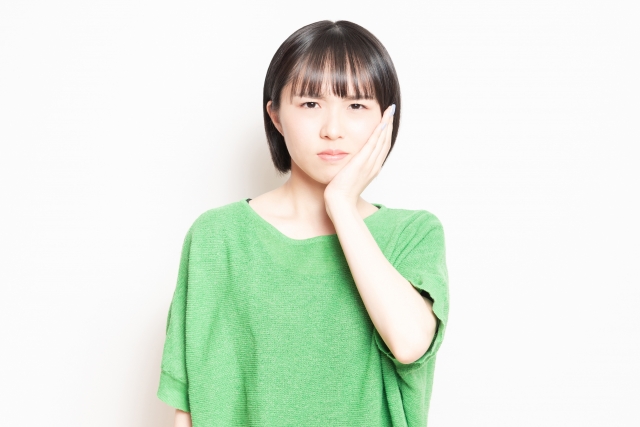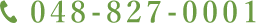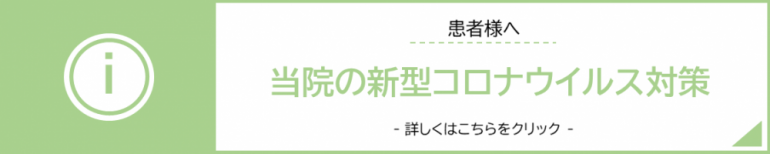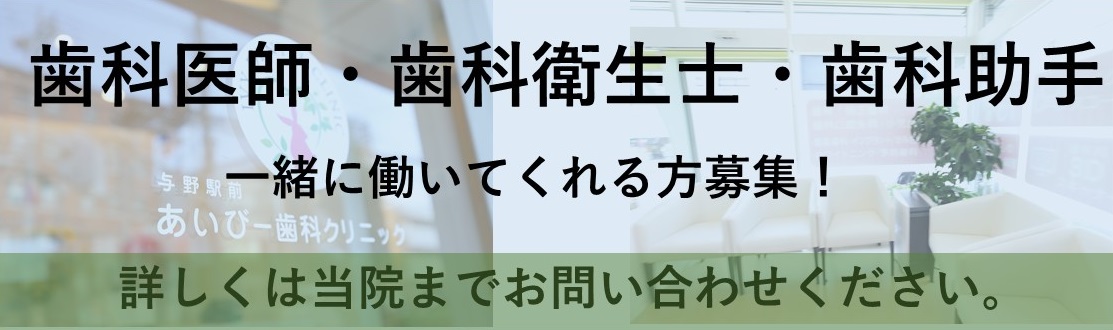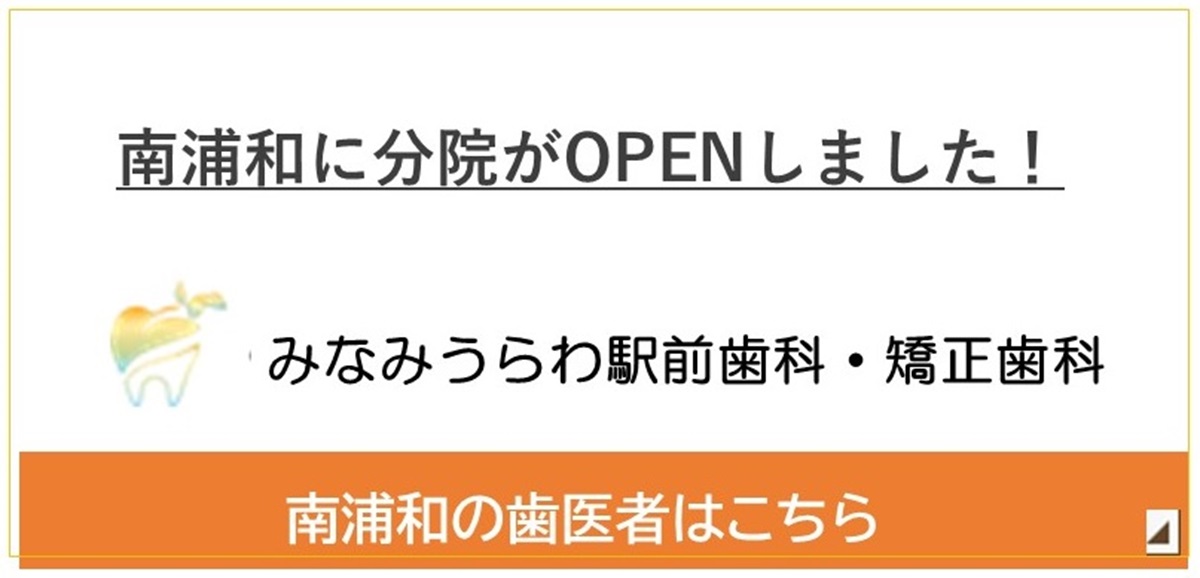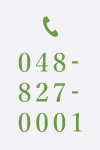レントゲンと歯科用CTの違い
2つの違いを簡単に説明すると、レントゲンは平面であるのに対して、CTは立体であることです。
レントゲンはX線を使用して歯や周囲の組織の画像を生成します。一方、歯科用CTは、X線源と検出器が回転しながら複数の断層画像を撮影し、それらの画像をコンピュータで組み合わせて立体的なイメージを作り出します。平面的に写るレントゲンでは、前後に並んでいるものは重なって撮影されます。そのため、色の濃淡で前方にあるのか後方にあるのかを判断します。 一方、CTは立体的に撮影しますので、病巣の位置や骨の内部、歯と顎の関係などすべてが様々な角度から確認することができます。3次元で見ることができるので、歯科医師だけでなく患者さんにも分かりやすいです。
歯科用CTは高い解像度で立体的な画像を提供できます。これにより、骨の詳細や歯の位置関係、根の形態などを正確に評価することができます。一方、レントゲンは2次元の画像を提供しますので、立体的な情報は得られません。
放射線量について、レントゲンは単一の2次元画像を撮影するため、放射線線量は比較的低いです。歯科用CTは、複数の断層画像を撮影するため、レントゲンと比べると放射線線量が多くなりますが、人体に影響がある量ではありません。
CTが役立つ症例
インプラント
インプラント治療では顎の骨に穴をあけてインプラント体を埋め込むため、顎の骨の状態、神経や血管の走っている位置、骨密度などを確認することが必要です。レントゲンでは把握できないところがあるため、インプラント手術前にCTを使用して精密に診断します。インプラントを埋め込む位置を正確に決めることができ、より安全に手術を行うことができます。 また、術前診断だけではなく、インプラントを埋入した後も必要に応じてCT撮影を行います。埋め込まれたインプラントの位置や状態、骨の状態などを確認します。
親知らずの抜歯
下顎の親知らずの近くには、下顎管という神経が走っています。抜歯するときには、この下顎管を傷つけないようにします。親知らずと下顎管との位置関係はレントゲンで確認することもできますが、把握できない部分もあります。例えば、歯の根の先と下顎管が重なっている場合、接しているのか、または前後で離れているかは正確にはわかりません。CTならさまざまな角度から確認できるので、より安全に抜歯を行うことができます。
根尖病巣の確認
虫歯が進行すると、歯の根の先端に膿の袋ができることがあります。この膿の状態をCTで確認することで、より正確に根の治療を行うことができます。
歯科用CTは上記の症例以外にもさまざまな場面で活躍しています。3次元の画像は非常に見やすく、治療の説明もより分かりやすくなります。特にインプラントや親知らずの抜歯を考えている方は、CT撮影を受けてみてください。